2025年10月、世界が注目するニュースが飛び込みました。
ノーベル化学賞の受賞者として、日本の化学者である北川進氏(京都大学特別教授)が選ばれたのです。受賞理由は、環境・エネルギー分野での応用が期待される「多孔性配位高分子(MOF)」の先駆的な研究です。
世界のCO₂削減にもつながる革新的な技術を生み出した北川氏の功績は、単なる科学技術の話にとどまりません。30年以上にわたる地道な研究、学生への情熱的な指導、日本の科学力の象徴──その歩みには、科学者としての信念と挑戦の歴史が刻まれています。
■ 北川進氏のプロフィール
北川氏は1947年、三重県津市に生まれました。京都大学大学院理学研究科を修了後、無機化学を専門とする研究者としてキャリアを歩み始めます。
1980年代には、米国でも研究経験を積み、国際的な視野を持ちながら独自の研究テーマを追求。1998年から京都大学教授、2013年からは特別教授として活躍してきました。
北川氏が世界的に知られるようになったのは、1990年代に入ってから。誰もが「夢物語」と考えていた「分子レベルのスポンジ」を実現したことが、科学界に大きな衝撃を与えたのです。
■ MOFとは何か?「分子のスポンジ」の正体
MOF(Metal–Organic Framework=多孔性配位高分子)は、一見すると難解な化学用語ですが、原理はとてもシンプルです。
金属イオンと有機分子が規則的につながってできる“骨組み”のような構造の中に、無数の「穴(孔)」が空いているのが特徴です。
この穴が非常に微細で、分子レベルで気体を吸着・貯蔵することができます。たとえば──
-
二酸化炭素(CO₂)を効率よく吸着し、地球温暖化対策に活用できる
-
水素を貯蔵して燃料電池などのエネルギー技術に応用可能
-
医薬品の成分を体内の必要な場所まで運ぶ「ドラッグデリバリーシステム」への利用も期待
つまりMOFは、「見えないところで地球を支える」素材なのです。
現在では世界中の研究者がMOFをベースに新しい材料や技術を開発していますが、その「原点」を築いたのが北川進氏です。
■ 「役に立つ」より「面白い」──ブレイクスルーまでの30年
北川氏がMOFの研究を始めた当初、化学界では「そんな素材は実現不可能」と見られていました。
なぜなら、分子を規則的に組み合わせ、しかも安定した構造として保つことは非常に難しかったからです。
しかし北川氏は「役に立つかどうかより、面白いかどうかで研究を選ぶ」という信念を持っていました。
失敗を重ねながらも、分子構造の精密な設計や結晶化の条件を徹底的に研究。
1997年、ついに世界初となる安定的なMOFの合成に成功します。
この成果は瞬く間に世界の科学誌で話題となり、北川氏は「MOFの父」と呼ばれるようになりました。
その後も北川研究室では、CO₂吸着やガス分離、水素貯蔵など、応用研究が次々と進み、環境・エネルギー分野のキープレイヤーへと成長していきます。
■ 研究者としての姿勢と教育への情熱
北川氏は研究者としてだけでなく、教育者としても高い評価を受けています。
多くの学生や若手研究者を育て、世界中に“北川門下生”が広がっています。
彼の研究室では、「一見、無駄に見える基礎研究」を大切にする文化が根付いています。
実用化を急ぐよりも、まず“科学として面白いこと”に全力を注ぐ。
この姿勢こそが、世界に誇るMOF研究の礎となりました。
■ 日本人ノーベル賞受賞のインパクト
日本人によるノーベル化学賞受賞は、科学界だけでなく産業界にも大きなインパクトを与えます。
特に、MOFはCO₂削減や水素エネルギーといったカーボンニュートラル社会の鍵となる素材。企業や自治体の脱炭素戦略においても重要な役割を果たすと期待されています。
政府関係者からも「世界の脱炭素社会をリードする技術」として高い評価が寄せられており、今後は研究開発投資の加速やスタートアップ企業との連携も活発化する見通しです。
■ SNSや世間の反応も大きな話題に
ノーベル賞発表直後、X(旧Twitter)やニュースサイトは北川氏の話題で持ちきりとなりました。
「ついにMOFの時代が来た!」
「環境対策に日本人の研究が役立つなんて誇らしい」
「北川先生、学生時代に講義を受けたことがある。すごく優しい人だった」
こうした声が相次ぎ、同時に「MOFって何?」と検索する人も急増。
難しい化学用語が一気に“身近なニュース”として注目される現象が起きています。
■ ノーベル賞は「ゴール」ではなく「通過点」
授賞会見で北川氏は、次のように語りました。
「この賞は、私ひとりのものではありません。長年、一緒に研究してきた学生や仲間、そして家族に感謝したい。MOFの可能性はまだまだ広がっていきます」
MOFはすでに数多くの応用が進んでいますが、さらなる進化も期待されています。
CO₂回収技術の効率化、クリーンエネルギー社会の実現、さらには医療や宇宙開発への応用も視野に入っています。
■ まとめ:「基礎研究が未来をつくる」
派手なテクノロジーの裏には、何十年も積み重ねられた地道な基礎研究があります。
北川進氏の言葉にもあるように、
「役に立つかどうかではなく、面白いことを追いかける」
──この信念が、やがて世界を変える発明につながりました。
日本の科学力、そして基礎研究の可能性を改めて世界に示した北川進氏。
この受賞をきっかけに、国内の科学教育や研究環境への注目がさらに高まることが期待されています。

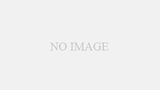

コメント